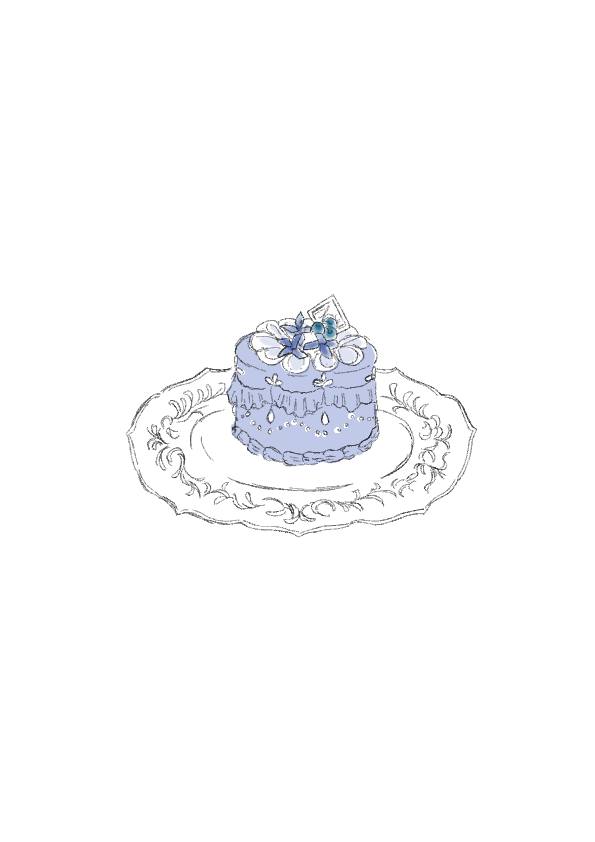「わあ、お店が全部キラキラしてる」
瑞花の街、宝石通り、なんて名前がついている所らしい。
「ここは昔からクリスタルを始めとした鉱物がとても沢山とれる地域でね。ジェム・アヴェニューは特産を使った建築が有名なんだよ……って聞いてないな。アンジュ、キョロキョロしてると危ない」
「私、クリスタルも好き」
隣で手を繋いでくるサヴィエを見上げた。
「なら俺はいい場所に家を建てたということだね。アンジュが気になるお店に入ってみようか」
まずは本屋さん。あまり向こうと変わらない感じがしたけど、勿論ラインナップは異なる。雑誌をペラペラと見たり、学問はどんなのがあるのかと見てみたり。小説コーナーに行けばサヴィエの本が平積みされていた。隣に居る人の服をひっぱって「売れっ子だね」というと、少し恥ずかしげに苦笑した。
「俺のは家にあるから買うなら他の、ね」
「はーい」
本屋では『極東:桜乃國・星洲』という遠い国のことが書かれた本と、『夢の中の夢』と書かれた絵本を買ってもらった。仕掛けが付いた絵本は子供の頃にとても好きだったことを思い出したのだ。
次に服屋さん。自分の好きなものもだけど、サヴィエに色々と着させられたりもして、結構おもしろかった。
「なんでもお似合いになりますね」
店員は片腕が骨で、からからと鳴らしながら接客してくれた。筋肉も皮もなしにどうやって繋がってるんだろうかと少し不思議に思うが、こちらにおいては向こうの常識は大して通用しないので難しく考えるのをやめた。
「そうでしょう。私もそう思います。これ全部」
「いや、全部はいらないよ」
「いつか必要になるかもしれないし、俺が見たいから買う」
「やば……」
案外浪費家なのかもしれない、と心配になる。
「次はどこを見たい?」
「お菓子屋さん。ケーキ屋さん?」
「俺のオススメがある。こっちだよ」
手を引かれて白い石畳を歩いていく。途中で真っ黒い服で、真っ白い笠を被った背の高い人がサヴィエに声をかける。顔がよく見えないけれど、優しそうな声だ。
「あらあらクォーツァ先生〜。可愛い子連れてますね」
「妻だよ、フフ……いてっ」
まだ結婚も何もしてないだろうが、と脇腹を突く。
「あら〜! 知らなかった!」
「アンジュ、この子は、私の生徒の一人で」
「ヒノエと言います」
ヒノエさんは笠をぴ、と上げて私を見て微笑む。肌も真っ白で手は鱗に覆われていて、赤い爪と黄色い目が映える。
「こんにちは。アンジュです」
「かわいーん。先生も隅に置けませんね! どこでこんなに可愛い奥さん見つけたんですかあ」
「内緒。ヒノエくんもかっこいい彼氏いるだろ?」
「可愛い彼氏ですよ〜。あ、デートのお邪魔しましたね! またゆっくりお話しましょうね」
ひらひらと細い手を振ってヒノエさんは建物の中に消えていく。
「あの子には文学を教えているんだ」
「へぇ。というか、スタイル良かったですね、さっきの方」
「……きみの感覚はとても素敵だね」
「?」
「こちらの話だ。……あ、あそこのいちごの看板が下がっているところだ。オススメのお菓子屋さん」
手を引かれてお店に入ると、甘い香りが鼻をくすぐる。
「いらっしゃいませ〜。あ〜、サヴィエせんせ〜」
店員さんがカウンターの向こうからヒラヒラ手を振っている。マスクやら帽子やらたくさんつけていて顔があまり見えない。ここの人からも先生と呼ばれている。サヴィエはやはり有名人なのかしら。
「こんにちは。今日はタルトまだあるかな?」
「ありますよぉ〜。どのフレーバーにしますかあ〜?」
のんびりした話し方の店員さんが、キラキラとガラスケースの中におさまって美味しそうなケーキをしめす。
「アンジュ、どれが食べたい? 好きなのいくらでも」
サヴィエは私が目を輝かせているのをみて微笑んで言う。
「え、迷う……。この、紫色は何ですか?」
一番に目を引かれたケーキをゆびさすと、店員さんがゆったーりと答える。
「ヴァン・ヴィオレ産の〜、菫の砂糖漬けです〜」
「美味しそうだね。それをふたつ」
横からすかさず注文していく。はやい。まだそれと決めてなかったけど、食べたいのには違いないのでいいか。私は書いてある商品名を見ながらうーん、と考えて、白いふわふわの乗っていて、きらきら銀色のゼリーが散りばめられているケーキを指さす。
「……これは?」
「わたぐもときららのタルトですね〜」
「ではこれもふたつ、あ、あとそれからいつもの焼き菓子を一箱分頼むよ。他には?」
訊ねるけれどそんなに沢山食べられないし私は首を横に振る。
「ない」
「はぁい、では、少々お待ちくださ〜い」
店員さんは喋りは緩いがテキパキ、ちゃっちゃか手を動かしている。梱包するのを見るのが好きで、じい、とカウンターの向こうで作業している店員さんを眺めていると、サヴィエの顎が私の肩の上に置かれる。
「なに?」
「何を熱心に見てるのかなと思って」
甘えられているような気がしなくもないな、と私は思ったがそのままに、店員さんがケーキの箱をぱぱっと閉じて、袋に入れるのを見ていた。
「お待たせいたしました〜。保冷魔法のかかっている箱なので、一日は持ちますよぉ。でも、なまものなのでお早めに召し上がりください〜。ええっとぉ、全部で四十五トポです〜」
「これで」
サヴィエはカードをぴ、と出して店員さんが受け取る。さっきも似たようなカードを出していたけど、私がいた世界で見る、いわゆるクレジットカードとは違う様子だ。これがここの紙幣なのかも。
商品を渡されて私が受け取る。
「はい。気をつけてお持ちくださいね〜。ありがとうございました〜」
「どうも、また来るよ」
サヴィエは器用に私から袋をとって、魔法で浮かせながら私の手を握り、店を出た。
「私も持つのに。サヴィエさんばっかり持ってる」
「アンジュは俺の手を持っててくれたらいいよ」
にっこり笑って沢山の袋をふよふよ浮かせながら言う。側から見たら面白い絵面だと思うけれど、魔力の無駄使い感は否めない。
サヴィエの屋敷に戻ると「お茶をご用意しますね」とどこか嬉しげなギュスターヴが、サヴィエと私のコートを奪い取っていく。
「談話室に行こうか。ギュスターヴがお菓子に合うお茶を淹れてくれるよ」
まだ暖炉の火が絶やせない日が続いている。ソファに腰掛けて温まっていると、ギュスターヴがサーヴィングカートに茶器やら何やらを載せて戻ってきた。
「さあ、ティータイムだ」
サヴィエがそう言って手をひと叩きするとティーカップが宙をとんで、私の前にやってくる。そこに注がれる香り高い紅茶。
「ミルクはいかがなさいますか?」
ギュスターヴが尋ねるので首を振る。サヴィエは楽しそうに今日買ってきたところの箱を開けて、わざわざ手ずから皿に菫のケーキとキラキラしたタルトを載せて、私に差し出す。
「アンジュはどちらが食べたい?」
「……こっちで」
小さな紫色の花が咲いたケーキを受け取ると、すかさずギュスターヴがフォークをテーブルに置いた。至れり尽くせりとはこのことかと、ポカンとしつつも、紅茶とケーキの良い香りにお腹が空いてくる。
「俺もこっちにしよう」
丸いケーキの上に乗った菫の砂糖漬け。それをすぐに食べてしまうのは気が引けて、フォークをちょっとだけその下に差し込む。
口に入れると、ブルーベリーの甘酸っぱさが広がる。紅茶を一口啜る。
「美味しい」
「そうだろう? 気に入ってくれてよかった」
サヴィエも頷きながらケーキを食べている。
もう一口、もう一口と食べ進めていくと、菫だけが残った。名残惜しくなりながらそれをゆっくり口に運ぶ。花の香りが口いっぱいに咲く。春がすぐそこに香っている。
「次は菫が咲いている場所に行きたいな」
ぽつりとつぶやいた私にサヴィエの手が止まった。不思議に思って私は飲もうとした紅茶のカップをソーサーに置く。
「……どうしたの?」
目を丸くしたサヴィエの頬に一筋涙が流れている。
「いいや……そうだね、次は菫を見に行こうね」